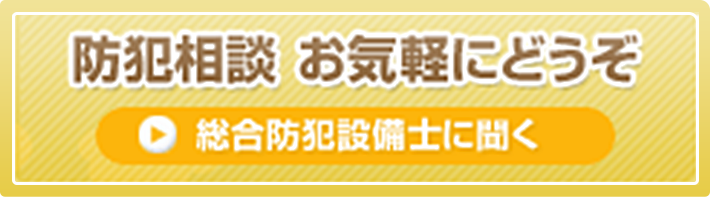今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
セコ過ぎる! 食にまつわるどケチ・セコい行動

最近、レジ袋有料化の影響で、スーパーの無料ビニール袋を大量に使ったり、果ては根こそぎ持って帰る迷惑な人が話題になっています。こうしたニュースを聞いて、まず頭に浮かぶのは「セコい」の三文字ではないでしょうか。そうです、この世界では、いつの世にも何となく「セコい」行動をする人がいます。
例えば、飲食店のつまようじや砂糖、はたまたホテルの備品などをごっそり持ち帰る人、「禁煙した」と宣言したのに、飲み会になると「1本ちょうだい」と毎回もらいタバコをする人、何でもかんでも経費で落とそうとするサラリーマン......。
ちょっと笑えるセコさから、それはちょっとヒドいんじゃないの? というものまで、今回は、実際にあった「食」にまつわるセコい行動のリアルな目撃エピソードをご紹介します。皆さんの周りにもそんなふうに微妙に「セコい」行動をする人がいませんか?
目撃談1. 会社のお菓子泥棒事件(30代男性・編集)
会社宛に来るお中元、お歳暮、はたまた、関係者からの手土産など、お菓子がオフィスに放出されている時ってありますよね。うちのオフィスでは出張土産の「八ツ橋」や「萩の月」などが、まるで煙のようにごっそり消えてなくなる事件が頻繁に発生していました。「あれ、さっきまでここにあったのに」「俺、食べてないけど」と、部内で何かと噂に。ところが、ひょんなことからネズミが発覚したのです。
ある朝、鎌倉の銘菓「鳩サブレー」が大きな缶ごと放出されていたのですが、ランチ時間の後、案の定、ほとんどがなくなっていたんです。しかし、とうとう目撃者からのタレコミが。「さっき、営業のY部長が両手で山ほど抱えてどっか行きましたよ」と新人のKくんが証言したのです。おそらくこれまでの「八つ橋事件」も「萩の月事件」も、他部署のY部長の仕業だったのです。
ところが、同日、3時ごろになると、Y部長は何食わぬ顔で「3時のおやつは何かな~」と「鳩サブレー」の箱の前に立ち、「あ~、もうこれだけしかないのかぁ」と白々しい独り言をつぶやき、「じゃ、1枚いただいちゃうよ」とひょいと持って行くじゃありませんか。セコいというか厚顔無恥というか、そんなに好きなら自分で買えよ、とみんなザワザワ。以来、Y部長は影でネズミと呼ばれるようになり、いただいたお菓子はロッカーに保管するルールになりました。
<9/22(火) 8:01配信 食楽webより>
どこの会社にもどケチ・セコい人はいます。
うちの会社にも思い当たる人は何人かいますが、不思議と役職が上の人がその傾向にあるような気が・・・。
一般社員や派遣社員と比べると毎月多くの給料をもらっていてお金に余裕があるはずなのに、本当に不思議です。
まあそれぐらいのセコさがないと出世ができない、お金も貯まらないのかもしれませんね。(悲しい現実です・・・)
上記で紹介されている記事は会社宛てに届いたお菓子を勝手に持ち去る部長の話ですが、お菓子の所有者は会社にあると考えると、誰の許可もなく持ち去る行為は窃盗とも言えます。(部長が自由にする権利があるとは思えません)
どこかに訴える内容ではありませんが、厳密にはそうだということを盗んだ人には認識してもらいたいものです。
個人の私物を勝手に拝借する人、食べ物、飲み物を許可なく食べる人、これって、正確には窃盗罪に当たるのではないでしょうか。
加害者が上司や先輩の場合、被害者は公にすることは難しいでしょう。いわゆる泣き寝入りというやつです。
盗んだ本人は、たかがお菓子ぐらいでガタガタ言うなという心情かもしれませんが、いざ自分が被害者の側になったら殊の外大騒ぎするものです。
いっそのこと、監視カメラを社内のあちこちに設置し、誰もが映像を確認できるようにしておけばこのような「菓子泥棒」は発生しなくなるでしょう。
これも監視カメラの有効的な使い方の一つです。
投稿者: 総合防犯設備士 (2020年10月30日 13:28)
犬の散歩中に石で車に傷つける21件
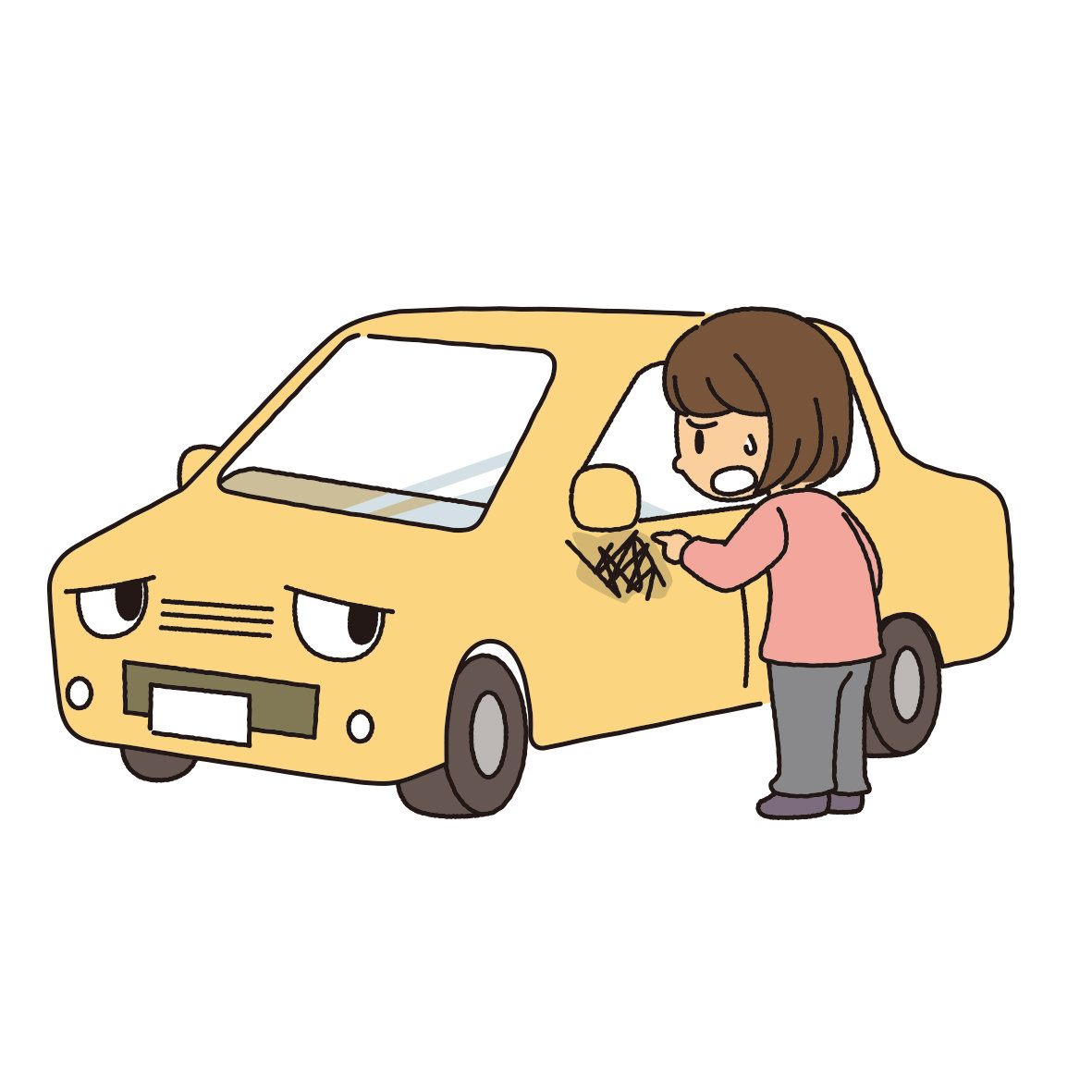
名古屋市緑区の路上で軽乗用車に石で傷を付けたとして6月3日、35歳の男が逮捕されましたが、防犯カメラが犯行の様子を捉えていました。
犬を散歩させる一人の男。歩道で石を拾うとあたりを気にしながら散歩を続けます。
そして、路上に停まっていた車に傷を付けました。
これは5月3日の夜、緑区内の住宅に設置された防犯カメラの映像です。
男は器物損壊の疑いで逮捕されました。
逮捕された近くに住む会社員の男(35)は、調べに対し、「ストレスが溜まっていたからやった」と容疑を認めています。
周辺では今年2月以降、同様の被害が21件相次いでいて、容疑者はいずれも認めています。
<6/5(金) 11:59配信東海テレビより>
夜、犬の散歩中に石を拾い、車に傷をつけて回る、という事件です。
ゴールデンウイーク中の犯行で、コロナ自粛でストレスが溜まっていたというのは分からなくはないのですが、実際に犯行に移すかどうかは大きな違いです。
また、違法な路上駐車に対して邪魔だからという気持ちからの犯行ならまだ分かりますが、普通に自宅に駐車している車に対しても犯行を行っており、弁解の余地はありません。
被害者側にとっての責任はゼロであり、加害者側に100%責任があります。
コロナ自粛も徐々に解除され、このようなストレス発散目的の犯行は減るでしょうが、また別のストレス(仕事や通勤、人間関係など)は増えるでしょう。
他人に迷惑を掛けない独自のストレス発散方法を見つけなければなりません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2020年6月26日 18:21)
暴力団勢力2万8200人に 10年連続で過去最少を更新

全国の暴力団勢力は昨年末時点で、前年比2300人減の2万8200人で、10年連続で過去最少を更新したことが2日、警察庁のまとめでわかった。暴力団勢力は2005年から年々減っており、同庁は「暴力団排除運動の広がりや取り締まり強化で活動資金の獲得が困難になり、離脱が進んでいる」と分析している。
警察庁によると、暴力団構成員は前年比1200人減の1万4400人で、暴力団と関係が深い準構成員は同1100人減の1万3800人だった。
組織別(準構成員を含む)では、6代目山口組が最多の8900人。次いで住吉会が4500人、稲川会が3400人、神戸山口組が3100人、1月に絆會(きずなかい)に改称した任侠山口組が600人で、こうした主要団体で全体の72・7%を占めた。
摘発人数(周辺者らを含む)は、前年比2600人減の計1万4281人。罪種別では、覚醒剤取締法違反が25・2%で最も多く、次いで傷害が12・8%、詐欺が10・1%、窃盗が10・0%だった。
今年1月、活動を大幅に規制する「特定抗争指定暴力団」に指定された6代目山口組と神戸山口組の抗争事件は15年8月の分裂以降、計124件発生(4月1日現在)。うち8件で9人が死亡している。両団体の抗争は「表面的には沈静化している」(警察幹部)が、再び激化する恐れもある。
近年は暴力団には属さない「半グレ」グループも繁華街などで違法行為を繰り返しているとして、警察当局は警戒を強めている。
<4/2(木) 12:37配信読売新聞オンラインより>
暴力団構成員1万4400人、順構成員1万3800人、合わせて2万8200人が全国の暴力団勢力ということです。
10年連続で過去最少を更新しているということですから、一般人からすると非常に喜ばしい状況であり、将来的には0に近い数字になることが望まれます。
ただ、これはあくまでも日本国内の数字であり、近年は国際化している組織もあるようで、今後は外国の暴力団、マフィア、麻薬組織等が日本で暗躍する可能性も考えられます。
暴力団勢力が弱体化することは良い面だけではないかもしれません。
例えば暴力団としての活動から、窃盗団に特化した活動にシフトする団体や個人も出てくる可能性があります。
彼らは暴力団ではなくなるかもしれませんが、別の犯罪をメインに活動することになります。
一概には言えませんが、暴力団として属していることで、ある程度の抑えが聞いている面もあるかもしれません。
その枠から出てしまうことで、抑止力となるものがなくなり、犯罪者としてはより活発に、より拡大してしまう可能性も考えられます。
単純に暴力団員を減らすことを目的にするのではなく、組織から離脱した者が別の犯罪に走ることがないように、社会復帰できる機会を与えられる社会にならなければなりません。
これがうまくいくと、犯罪が起こりにくい環境に自然と変わっていくように思います。
投稿者: 総合防犯設備士 (2020年5月 8日 16:17)
ニューヨーク 新型コロナの影響で犯罪も減る

【ニューヨーク時事】米メディアが報じたニューヨーク市警の集計によると、16~22日の市内の重罪事件は1337件で、昨年の同時期の1604件から16.6%減った。
市では新型コロナウイルスの感染拡大を受け、在宅勤務が増加。16日には公立学校と飲食店(持ち帰りと配達を除く)が閉鎖になり、市内は普段より出歩く人が大幅に減っていた。
殺人、レイプ、強盗、暴行、住居侵入窃盗、窃盗、車窃盗のうち、車窃盗以外は軒並み減少。
車窃盗は昨年同時期の68件から103件に増えた。
ニューヨーク市警のシア本部長は24日の記者会見で「多くの犯罪が依然起きている。それを引き続き発信するべきだ」と強調した。
<3/25(水) 14:21配信時事通信より>
新型コロナウイルスの影響で不急不要の外出をする人が減り、人と人の接触する頻度が減っているのですから、犯罪件数が減るのは当然です。
日本でも学校が休校となり、また、休みの日も外出する人が減ると、家で過ごすことが多くなります。
つまり、家に人が居る状態が多くなります。
逆に店舗や事務所には人が居る状態が減ることになります。
テレワーク等で事務所には出勤せず、自宅で仕事をする人が増えてくるでしょう。
店舗や事務所に人が居ないとなれば、平日でもそこが狙われる危険性があります。
平日の一般住宅に人が居るということはそこを狙っての侵入窃盗はリスクがあります。
通常は人が多い店舗や事務所を狙っての犯行に切り替える泥棒もいるでしょう。
店舗や事務所の無人時の防犯対策が必要となります。
また、一般住宅に関しては、人が居るから安心とも言えません。
例えば、深夜、家人が寝静まった状態をあえて狙おうとする泥棒も増える可能性があります。
金品が奪われるだけで済めば不幸中の幸いで、もし家人が侵入者と出くわしてしまった場合、凶器を持っていれば殺傷される可能性があります。
強盗対策も視野に入れた防犯対策が必要かもしれません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2020年4月24日 16:59)
マスクの流通量

今泥棒に何が人気かと聞かれれば、まずマスクが思いつきます。
それ以外にはアルコール消毒液やデマで品薄のトイレットペーパーなどでしょうか。
新型コロナウィルスの騒動で感じたことは、この日本は意外に物が少ないということです。
物にあふれている、物が過剰にある、というように言われたこともあったと思いますが、マスクがあっという間に姿を消し、もう1ヶ月以上買えなくなっています。
工場では不休で増産しているというニュースも見ましたが、その増産したマスクはどこに行っているのでしょうか。
ちょっとしたデマ情報がSNS等で拡散すると、人々は混乱し、多くの人がその商品を買いに走ります。
その様子がまた報道され、全国的に品薄となり、あっという間に店頭から姿を消します。
その状態が数日で解消されればよいのですが、解消されるまで、つまり市場に流通するまでに時間が掛かることが多いように思います。
そう考えると、通常の購買活動以外に少しでも需要が高まると、すぐに供給を追い越してしまい、物が不足することが多いという状況なのでしょうか。
品薄状態を敏感に感じ取った人が、転売目的で買い占め、そして高値で転売するチャンス狙っているとも言われていますが、そのような人が何万人もいるとは思えません。
個人的には、政府やメーカー、工場、卸売業者等が不当に流通量を制限し、そして長期的に一定量を販売するためにどこかに保管しているような気がしてなりません。
今の品薄状態であればどこの家でもマスクを何箱か置いておきたい気持ちがあります。
それを逆手にとって流通量をコントロールし、少しずつ流通させ、そこに人が群がる状態を長引かせることで、この騒動が収束した後も売り続けようとしているような気もします。
あくまでも個人的な感想で、本音を言えば早く買えるようになればいいのに、という気持ちです。
投稿者: 総合防犯設備士 (2020年3月19日 15:18)
無施錠宅を探して侵入 性的暴行未遂の男逮捕
アパートの鍵のかかっていない部屋に侵入し、10代の女性に性的暴行を加えようとしたとして、アルバイトの男が逮捕された。
警視庁によると、男は先月、東京・世田谷区にあるアパートの部屋に侵入し、寝ていた10代の女性に性的暴行を加えようとした疑いがもたれている。
男は鍵のかかっていない部屋を探して侵入したとみられ、女性が抵抗すると逃走したという。調べに対し、容疑を認め、「酒の勢いでやってしまった」と供述しているという。
世田谷区では同じ日に別の住宅でも女性が襲われる事件が起きていて、警視庁が関連を調べている。
<11/22(金) 14:14配信日テレNEWS24より>
犯罪を計画し実行する犯罪者と、酒や薬の影響で犯罪を犯してしまう者、どちらも犯罪者ですが、それに対する対策は異なってきます。
犯罪を計画する犯罪者は、事前に現場を下見するなど、侵入から逃走までを考えてトータル的に犯罪を行います。
それに比べて、酒や薬の勢いで犯罪を犯してしまう者は、計画的ではなく、衝動的、発作的な犯行が多いと言えます。
前者の場合、自分が捕まらないことも重視していますから、下見の段階で犯行ターゲットを選別します。
防犯カメラや防犯システムなどが設置されている現場は避けた方が安全です。
一方、後者の場合、衝動的にその場で思いついての犯行(覚えていない場合もあり)が多いと考えられますから、防犯対策では犯行を防ぐことができない場合があります。
もちろん、防犯システムが鳴動し、それ以上の犯行が不可能になる場合もあるでしょうが、防犯カメラなどの受け身の対策では、無視して犯行を強行される場合があります。
酒だけでなく薬(ドラッグ)の使用者による犯罪も日本において増えてくる可能性があります。
薬関係で逮捕される芸能人や有名人のニュースが後を絶ちませんが、一般の人も含めて薬が身近なものになっているのは間違いないでしょう。
合法ドラッグという名前のものがあることからも様々な種類のものがあり、またそれらの混合物なども考えると、恐ろしい話ですが知らずに摂取させられるケースも考えられます。
投稿者: 総合防犯設備士 (2019年12月20日 16:45)
女装の男が女子トイレに侵入
常総署は8日、建造物侵入の疑いで、千葉県野田市、会社員、男(40)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日、常総市新石下の衣料品店女子トイレに侵入した疑い。同署によると、同市内では9月中旬ごろから女装した男による付きまといなどの不審者情報が寄せられたため、県警が配信する防犯メールなどで、市民に注意を喚起する一方、通学時間帯の警戒活動を実施していた。
同日、関東鉄道常総線新石下駅付近に女装した男が車から降りて付近を徘徊(はいかい)した後、衣料品店の女子トイレに侵入したのを警戒中の捜査員が見つけ、取り押さえたという。
<11/8(金) 21:27配信茨城新聞クロスアイより>
ドラマや映画などでLGBTの登場人物がいることは珍しくありません。
彼らが主役の場合もありますから、彼らへの理解はかなり進んでいるように感じます。
ただ、そのことを犯罪者が悪用する可能性もあります。
例えば、普段女装する人を見かけてもそれほど違和感はなくなってきたように思います。(あまり見かけたことはありませんが・・・)
それを悪用して、犯罪者が変装目的で女装し、その姿のまま犯罪を行うということも考えられます。
偏見や差別がなくなることはどの国、どの地域でも歓迎すべきことです。
ただ、それを悪用しようと考える者の存在を忘れないようにしなければなりません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2019年12月13日 18:17)
店舗のキャッシュレス化とセキュリティの関係性
「キャッシュレス・ポイント還元事業」が2019年10月より始まり、1カ月がたちました。ステッカーも行き渡ったようで、今まで現金決済オンリーだったお店でもステッカーを目にするようになりました。これを機にほとんどのお店でキャッシュレス化が進めば便利だなと思っていましたが、いまだにレジで「ウチのお店は現金のみなんです」と言われることもあります。
キャッシュレス化に踏み切る店と、現金主義を貫くお店の違いは何だろうと考えてみたところ、気付いたことがありました。
顧客に対する想像力があるか
今まで現金決済のみだったのに今回キャッシュレス決済に踏み切っている店は、「お客さまへのサービス精神」が強いお店だと感じました。
お店側としては従業員全員の制度理解や使用方法の説明にかける時間、初期費用や手数料などのランニングコストが一番のネックとなるのだと想定されます。ただ、現在ではかなり気軽に始められるものもある中、現時点で現金決済のみにこだわっているお店はとても疑問に感じます。お客さまの支払方法を、店側の都合で決めているからです。
どこまで対応すればいいのか分からないというお店に関しては、まずは自分たちにできる範囲で少しずつ対応すれば良いと思います。QRコード決済、クレジットカード、電子マネーなど最初から全ての決済手段を網羅するのはさすがに難しいかもしれませんが、自店の顧客層や立地なども考慮して、可能なところからクリアしていくべきだと考えます。
消費者にとってはお得になり、お店にとっては呼び水となるポイント還元はいずれ終わります。ですが、キャッシュレス決済の流れ自体は今後も止まらないはずです。既に海外でも日本よりキャッシュレス化が普及している国は少なくないですし、インバウンド需要、強盗などの犯罪リスク、店舗セキュリティを考えても、現金を使用する機会はもっと少なくなっていくと思っています。
店舗へ行くリストからは外され、仕事も増えている
普段お財布を持ち歩かない人からすれば、現金決済のみのお店は自動的に選択肢から外されがちです。実際に私や周囲の知人でも、買物をする際にはクレジットカードや電子マネー決済が中心となっています。
もちろん、決済の不便さを補うだけの「ウリ」や「理由」がお店にある場合は別です。どこにも負けないサービスがある、絶品こだわりのメニューがある、レトロな空間なのであえてカードリーダーなどの端末は扱いたくないなど、強い意思を持った理由がある場合は、現金決済でもお客さまには困らないと思います。ただ、大半の店はそうではないはずです。
そういったお店の場合、最終的にはお店側がお客さまの立場で見ることができるかどうかだと思っています。
「今まで現金を使うお客さましか来なかったからうちには必要ない」と思っているお店は、単にキャッシュレス決済を利用するお客さまから敬遠されている可能性も高いです。実際、私自身も財布を忘れてしまったときや手元に現金が少ないときは、店外から見て必ずクレジットカードが使えるお店を選んでいます。
言い換えれば、自分たちのコストや手間を気にして現金決済にこだわっている結果、一部のお客さまの選択肢から自店が除外されているともいえないでしょうか?
お客さま側からすれば、キャッシュレス決済なら自分のお金の使用状況を簡単に把握できます。使用履歴はそのまま家計簿代わりにもなりますし、レジで小銭を数える手間もなく、何より楽です。それぞれで行われているポイント還元は割引と同様なので、価格に敏感な層にとっては「キャッシュレス決済を使える店を選ぶのが当たり前」にすらなってきています。
お店側としても、日々の現金管理やレジ対応でお釣りを数えて渡すなど1客当たりにかける時間、前述した顧客減少や犯罪のリスクを考えれば、手数料やランニングコストをかけても導入するだけのメリットは決して少なくないように思います。いずれ導入するのなら、注目が集まっている今この時点で導入すべきだと考えています。
覚える、登録する手間がかかるから現金決済にこだわり続けるのか、お客さまの利便性を考えて踏み切るのか。いまだに現金決済のみのお店は、顧客に不便を強いても来店してもらえるだけの魅力や覚悟が本当に自店にあるのか、改めて考え直してみてもいいのではないでしょうか。
<10/31(木) 5:00配信商業界オンライン>
防犯センサーや防犯カメラを設置するセキュリティ対策と、パソコンなどに対するネットセキュリティ対策は別物と考えられていましたが、それぞれの関連性は増しているように思います。
キャッシュレス決済等を行う際、ネットセキュリティ対策は必須です。
パスワード等の重要な顧客情報が流出するのは致命的ですから、店側は必ずその対策を行わなければ顧客の信用を失ってしまいます。
今回の記事にあるように、キャッシュレス化が進むことで、店舗に置いておく現金の金額は少なくなります。
そのことによって、現金を狙う窃盗犯、強盗犯が減るのは間違いありません。
現金がない店を狙っても仕方がないからです。
ある面では、キャッシュレス化によって店舗のセキュリティ対策が行われているとも言えます。
但し、宝石貴金属店など高額商品を置いている店舗は、現金が少なくなっても商品が狙われる可能性がありますから依然としてセキュリティ対策は必須です。
ある一つのシステムの導入によって、複数の効果が実現できれば導入しやすくなります。
キャッシュレス決済の導入によって、利用客が便利になり増加する、強盗や窃盗犯に現金が狙われる可能性が低くなる、現金を銀行に預ける頻度が少なくなる、これは導入が促進される要因として充分かもしれません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2019年12月 5日 18:50)
男子高校生が就寝中に切りつけられる 犯人は知らない男
埼玉県蕨市の民家で16日未明、高校2年の男子生徒(17)が侵入してきた男に首を切られた事件で、男子生徒が「知らない男だった」という趣旨の説明をしていることが、捜査関係者への取材で明らかになった。
逃げていく男を目撃した父親も「面識がない」と話しており、県警は周囲の防犯カメラを調べるなどして男の行方を追っている。
捜査関係者によると、民家前のフェンスに何かがこすれたような跡があり、その上にある2階のベランダには何者かの足跡があった。
窓は無施錠だった。
県警は、男がフェンスに足をかけ、脇にある電柱を登ってベランダに飛び移り、窓から侵入した可能性があるとみて調べている。
県警によると16日午前3時半ごろ、民家2階の自室にいた男子生徒が男に首を刃物で切られ、約2週間の入院が必要なけがをした。
ベッドに血痕があり、男子生徒に抵抗した際にできる傷が見当たらないことから、県警は男子生徒が就寝中に突然男に切り付けられたとみている。
男は襲撃直後、1階玄関から逃走した。刃物を持ったまま逃げているとみられる。
<7/17(水) 17:55配信 毎日新聞より>
男子高校生が自宅で就寝中に何者かに首を切りつけられた事件ですが、犯人とは面識がないということですから一体どのような犯行動機だったのでしょうか。
窃盗目的で侵入したら男子生徒が就寝していたため、そのまま逃げたという事件なら分かるのですが、わざわざ寝ている男子生徒を切りつけて、自分の顔を見せるリスクを犯しているところに合点がいきません。
男子生徒本人もしくは家族への怨恨目的でしょうか。
現時点では犯行動機は不明ですが、非常に恐ろしい事件と言えます。
女子生徒なら暴行目的等の犯行も考えられますが、男子生徒ですからその可能性も低くなります。
誰が狙われてもおかしくない事件ということになります。
これからの季節、就寝時に窓を開放するところが多いと思いますが、窃盗目的以外で犯罪者が侵入してくる可能性も想定しなければなりません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2019年8月23日 18:04)
神奈川 パン製造会社に無断侵入した男逮捕
正当な理由なく建物に侵入したとして、神奈川県警大和署は17日、建造物侵入の疑いで、住所不定、自称塗装工の男(27)を逮捕した。
「弁護士が来てから話す」などと供述している。
逮捕容疑は同日午前3時15分ごろ、同県大和市中央林間西にある調理パン製造会社の建物内に無断で侵入したとしている。
同署によると、同時間帯に同社を訪れていた納品業者の男性が、誰もいないはずの社内から明かりが漏れていることに気付き、110番通報した。
同署員と自動車警ら隊員数人が駆けつけると、男は正面玄関から飛び出し、同署員1人に催涙スプレーのようなものを吹きつけて逃走したが、直後に身柄を確保された。
スプレーを浴びた同署員は病院で診察を受けたが、けがはないという。
同署は男が金品を狙って同社に侵入したとみて、余罪の有無を含めて捜査する方針。
<6/17(月) 19:02配信 産経新聞より>
パン製造会社に侵入した男が逮捕されました。
金品を狙っての侵入とみられていますが、もし異物混入等が狙いの場合、製造した商品全てが犯行対象となり、もし出荷済み、市場に流通済みの場合は、それらを回収するリスクも生じます。
またお客様への謝罪やお詫びの補償として商品券や金券を提供することもあり、事件によっては多大な損害を企業側に負わせることになります。
侵入されたという被害者にも関わらず、まるで自分が加害者かのように謝罪しなければならない事態は、企業側にとってもやり切れない、納得がいかないことでしょう。
ただ、今回の事件をみても、場合によってはそのような事態に陥ることは可能性として決して低いものではないように思い、現実としていつ発生してもおかしくない事件と言えます。
万が一の被害としてではなく、実際に起こりうる被害として捉え、具体的な防犯対策によって防衛しなければなりません。
特に、今の犯罪は犯罪者側の動機が様々で、単なる金品目的、嫌がらせ目的のような単純なものから、例えば、インスタ等のSNSや動画サイトにアップし、注目を浴びたいという欲求を満たすための犯罪(本人にとっては犯罪という意識が薄い、もしくはない)もあります。
このような事件に巻き込まれないためにも対策を講じなければならないでしょう。
投稿者: 総合防犯設備士 (2019年7月19日 11:02)