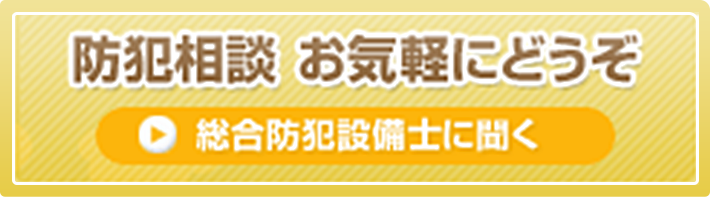今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
みんなでお金を集めてプレゼント 多めに集金するのは横領罪?

卒業式でクラスのみんなから、担任の先生に花束を渡すという学校は少なくないと思います。微笑ましい光景ではありますが、一方で、お金の徴収に関する投稿が話題になっています。
Xで注目を集めた投稿の情報をまとめますと、1人あたり1000円の徴収があったけど、「余らないってことあるの?」と疑問を呈するものでした。領収書などは見せてもらえなかったそうです。
この投稿に対して、「(花束は)せいぜい5000円くらいなんじゃないかな」「最初からポケットマネーにしようとしているのでは」「自分だったら収支明細を作成してる」といった声があがっています。
春は卒業式や歓送迎会などで、プレゼントや花束を渡す機会が増えるシーズンです。飲み会や会食などもあり、複数の人からお金を集める場面がよく見られます。
しかし、どのように使ったかなど、不明瞭なケースでは疑問も生まれるでしょう。弁護士ドットコムにも、「数十人規模の飲み会で、1人2000円しかかからないのに、1人5000円と偽って集金して幹事で山分けしようとしています」といった相談が寄せられています。
もし意図せずお金が余った場合、とりまとめた人がそのままもらってしまっても良いのでしょうか。また、あらかじめ多く集金して、余ったお金を幹事がポケットマネーにすることに法的問題はないのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。
●余ったお金をポケットマネーにしたら?
卒業式が終わり、入学式のシーズンですね。卒業されたみなさま、入学されるみなさま、本当におめでとうございます。私は花粉症で涙する日々が続いています。
さて、卒業式で花束を買う目的で集めて、花束の代金と差額が生じて、お金が余った場合です。
一定の目的でお金を預かって、余ったお金を勝手に使えば、横領罪に問われる可能性があります(刑法252条1項/5年以下の懲役)。横領罪というのは、預かったものを「自分のものにする犯罪」です。
余ったお金は本来返すべきお金ですが、返すべきお金を自分のものにしたと判断される余地はあるでしょう。
なお、実際問題は、そこまで大金でなければ、お金を預けた側も大きな問題にすることはないでしょうし、余ったお金はとりまとめてくれた人への御礼にすることもあると思います。念のため、余った場合のことを伝えておくほうが無難ですかね。
●もらう目的で「多めに集金」は絶対やめて
次に、あらかじめ多く集金して、余ったお金を集めた人がもらう場合についてです。
余ったお金を自分のために使おうと考えつつ、みんなに内緒にして、あえて花束代よりも高い金額を伝えてお金を受け取った場合、「欺いて」財物の交付を受けたとして、詐欺罪に該当する可能性があります(刑法246条1項/10年以下の懲役)。
通常、このようなケースは少ないとは思いますが、絶対にやめてください。
めでたいことなのに、こんなことで人間関係が崩れたりするのはよくないですからね。親しい間柄でも、お金の授受は慎重にしましょう。
<4/2(水) 10:21配信 弁護士ドットコムニュースより>
ひとり○千円だしてプレゼントを買って送別会で渡そう、どこの会社やサークルでも見られる光景です。
そのお金を多めに集めて、残ったお金を自分の物にしようとする厄介な人がいるという記事です。
結果として集めたお金が余り、自分の物にする場合と、最初から多めに集めるのでは全く意味が違ってきます。
少し内容は異なりますが、以前会社の飲み会でひとり3千円ずつ徴収し、その分を経費で落としていた人がいました。
防犯の会社に勤めている人が、会社で泥棒行為を行っている、嘆かわしい状況に多くの社員が悲観していました。
その人は数年前に退職しましたが、横領が発覚しての懲戒解雇だったのではないかという噂でした・・・。
一部の地位の高い人が行ってきた職場での各種ハラスメントに業務上横領や不正行為、多くの人が見て見ぬふりをして我慢してきました。
しかし、コンプライアンスが重視され、また情報が世界中に発信される時代になり、内部では許されても外部(世間)が許さなくなってきました。
個人的にはとても良い傾向で、罪を犯した悪人が罰を受けて追い出され、善人が救われるというのは健全で好ましいことだと思います。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月29日 14:43)
意外に知らないゴルフ場での法律違反 ロストボール持ち去りは? カートの飲酒運転は? ビールを賭ける?

ロストボールを持ち帰ると窃盗罪に該当する?
昨今はオレオレ詐欺や闇バイトのような卑劣で許しがたい犯罪が増えていますが、大多数の方は犯罪とは無縁の生活を送っているはずです。その一方、もしかしたら"知らず知らずのうち"に犯してしまっている法律違反があるかもしれません。
では、ゴルフにおいて、そういった可能性がある行為はあるのでしょうか。自身もゴルフを嗜んでいる旧知の弁護士に話を聞いてみました。
「軽犯罪法に該当する可能性がある身近な例としては、建物や森林の近くで焚き火を行う(同法第1条9号)、行列に割り込む(同法第1条13号)、道路に唾を吐いたり嘔吐したりする(同法第1条26号)といったものがあります。いずれも1日以上30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料、いわゆる罰金が科される可能性があります」
「ゴルフでは、ロストボールの持ち帰りがしばしば話題になりますね。林などに打ち込んでしまった際にはロストボールと遭遇するケースも多く、比較的キレイなボールや高価なボールは、ついでに拾ってくることもあるかもしれません。また、たとえ自分では使わないとしても、ボールを無くしやすいビギナーにあげたりすることはよく見られる光景ともいえます」
「しかし、この時点におけるロストボールの所有権は、元々の持ち主からゴルフ場に移っています。そのため、拾ったロストボールを持ち帰ったりすると、厳密にいえば窃盗などの罪に該当する可能性があります(刑法第235条)」
「現実的には、ロストボールを数個持ち帰ったからといって、よほど悪質でない限り、ゴルフ場がゲストを訴えることは考えづらいでしょう。とはいえ、ロストボールの扱い方としては、『そのまま放置して立ち去る』or『キャディーさんに渡す』or『マスター室に届ける』といった手段を選んだ方が賢明でしょう」
ゴルフカートの運転や"オリンピック"も要注意
ロストボール以外の法律違反としては、「ゴルフカートの飲酒運転」が気になるかもしれません。道路交通法第65条第1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されていて、違反した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
その一方で、ゴルフ場のカート道は"公道"ではないので、場内に限っていえば、法律上は飲酒運転の罪に問われることはないそうです。
ただし、セルフの乗用カートを利用する際は、プレー前に「安全運転誓約書」への承諾がプレーヤー全員に必要となり、そこには「飲酒をしてカートを運転しない」という項目も含まれているはずです。そのため、もしもランチなどで飲酒する場合は、「お酒を飲む人は運転しない」もしくは「あらかじめキャディー付きでラウンドする」といった節度ある行動が求められます。
最近では、熊本県の県議ら13人が、「賭けゴルフ」の疑いで書類送検されたこともニュースになりました。ゴルフでは、"オリンピック"や"ラスベガス"といったゲーム性の高いプレースタイルもありますが、賭けゴルフは賭博罪(刑法第185条)として扱われるケースがあるそうです。
ここでいう賭博とは、「偶然の勝敗によって、財物や財産上の利益の得失を争う行為」を指します。刑法第185条では、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」と定められていますが、「ただし、一時の娯楽に供する賭けにとどまるときは、この限りでない」とも記されています。
たとえば、「負けた方がランチやビールを奢る」といった行為は一時の娯楽にあたるので問題ない一方、プレーヤーが参加費として出し合った「賞金」やスコアの良い人を予想する「馬券」などは、すべて賭博に該当してしまいます。過去には「1口200円」という少額にもかかわらず、賭博罪として書類送検された判例もあるなど、金額の大小にかかわらず、現金はすべてNGとなります。
法律のプロから聞く話は、身が引き締まるものが多いですが、もちろん法律の原則としては「知らなかったから」は通用しません。"知らず知らずのうち"に法律違反しないよう、最低限の知識を持ったうえで、良識のあるゴルフライフを楽しんでいきたいものです。
<4/16(水) 11:10配信 ゴルフのニュースより>
ゴルフ場のロストボールを持ち去ったら窃盗罪に問われる可能性があるということです。
ゴルフ場側は回収したロストボールを販売することもあるようで、所有権が元々の持ち主からゴルフ場に移っているため、見つけても勝手に持ち去るのはいけないということで納得です。
また、勝負で負けた方がランチやビールを奢るといった行為は一時の娯楽にあたり問題ないようですが、参加費を出し合った賞金などは賭博に該当してしまうようです。
一口200円という少額でも賭博罪で書類送検された例もあるようで、金額の大小にかかわらず現金を渡すのはすべてNGということです。
参加費を集めて入賞者に賞品や景品を渡すのは大丈夫そうですが、あまり高額だと問題があるようです。
ゴルフに限らず何らかのゲームやスポーツをやる際、参加者同士で冗談っぽく賭けのようなことをする場合がありますが、勝った人に昼食や夕食を奢るのはOKで、現金を渡すのはNGと考えたらよいでしょうか。
このあたりの判断基準はあいまいな気がしますので、場合によっては賭博罪になってしまうこともありうるため注意が必要です。
最近では芸能人のオンラインカジノの利用が話題になりましたが、日本においては競馬、競輪、競艇はOKだが、賭け麻雀やサイコロ賭博はNG、でもサッカーくじやパチンコはOKと、それぞれ明確に法で定められているのでしょうが、一般の人には分かりにくいのが現状です。
また、個人がオンラインゲームに課金する行為も常習性や中毒性を考えると共通点があるように思います。
たばこやアルコール、薬物、そしてギャンブルと個人の嗜好や趣味の範囲内で収まるものとそうではないものの境界があいまいになりつつあるような気がします。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月22日 10:29)
市バス元運転手 運賃1000円着服し退職金1200万円不支給確定

バスの乗客が支払った運賃1000円を着服したとして、懲戒免職となった京都市バスの元運転手の男性(58)が、市に約1200万円の退職金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は17日、処分が重すぎるとした2審判決を破棄し、退職金不支給は適法とする判決を言い渡した。男性の逆転敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。
判決によると、男性は2022年2月、乗客から受け取った1000円札を運賃として処理する精算機に納めず、制服のポケットに入れて着服。市交通局が業務点検でドライブレコーダーを確認して発覚した。
小法廷は、公金の着服は重大な非違行為で、1人で乗務する運転手には運賃の適正な取り扱いが強く求められると指摘。着服でバス事業に対する信頼は大きく損なわれるとし、1200万円の退職金全額を不支給とした処分に「裁量権の逸脱はない」と結論づけた。
京都地裁判決(23年7月)は不支給処分を適法としたが、大阪高裁判決(24年2月)は着服金額が少額で、被害弁償もされていることから処分を取り消していた。
<4/17(木) 15:01配信 毎日新聞より>
市バスの運転手が乗客の支払った運賃1000円を着服し懲戒免職となり、退職金1200万円の不支給処分の取り消しを求めた訴訟ですが、不支給は適法という判決が確定したという記事です。
1000円を手に入れるために1200万円を失っただけでなく、定年まで勤めることで得られた賃金数千万円(3年前の事件当時の年齢で、定年60歳なら5年間分、定年65歳なら10年間分)を失ったという大損の結果となりました。
また、懲戒免職という結果は男性の経歴に大きな傷となり、その後の再就職にも影響を及ぼすことでしょう。
1000円を着服するという魔が差した行為(罪)に対して、その時には想像もしない罰が与えられてしまいました。
単純に損得で考えると、あまりにも割に合わない結果ですが、犯罪を犯すという行為は得てしてそういう傾向にあるものです。
例外的なものとして、今日の食事もままならない、あとは餓死するしかないそのような状況に追い込まれれば、それを犯罪行為によって挽回しようとする、利を図ろうとすることはある程度理解できます。
自分も同様の状況に陥れば、生きるために何らかの犯罪を犯してしまう可能性はあります。
そうではなく、自分が少し得をしたい、楽をしたい、という利己的な欲望のために犯す犯罪は、頭で「想像」し、行動として「実行」する際、そのリスクを充分に検討し、本当に冒す価値があることなのかを冷静に判断してほしいものです。
その結果、その場での犯罪を思い留まれば、犯罪の「抑止力」になったと言えますし、犯罪件数を減らすことにつながれば、犯罪を防ぐ「防犯」になります。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月15日 09:06)
「ゴルフ場の駐車場」防犯カメラは設置しない?

全員が自家用車で来ても問題ない広さは確保されている
ゴルフ場への交通手段として最近は電車やクラブバスを利用する人も増えていますが、やはりマイカーで向かう人が大半を占めているはずです。
みんながクルマを使って行くのであれば相当な台数をとめられる駐車場が必要になりますが、ゴルフ場の駐車場のキャパシティーがどのくらいあるのか興味がある人もいるかもしれません。
では、ゴルフ場の駐車場は何台程度のクルマをとめられるのでしょうか。ゴルフ場の経営コンサルティングを行う飯島敏郎氏(株式会社TPC代表取締役社長)は、以下のように話します。
「一般的な18ホールのゴルフ場の場合、1日あたりの利用人数を考慮して、200台程度はとめられるように造られています」
「『2サム』や『3サム』も増えてはいますが、ゴルフのラウンドは1組4人で回るのが基本であり、1日に受け入れるべき最適な組数は50組とされています。そこで50組すべてが4サムとなっており、なおかつゴルファー一人ひとりが自分でクルマを運転してきたと仮定すれば、200台はとめられるようにしておいた方がいいだろうという考え方が広まっています一般的です」
「一方で、同じ組で回る仲間で相乗りしてくる人や、電車とクラブバスを乗り継いでくる人も多いので、『そこまで必要ないのでは?』と思う人もいるかもしれません。しかし、大規模なコンペなどが開催される際には満車に近い状態にもなるため、後になって『全く駐車マスが足りない』というトラブルを防ぐためにも、多くのゴルフ場ではできる限り200台分のスペースを確保するようにしています」
また、もしも駐車場が満車になってしまった際には、ゴルフ場の入り口からつながる進入路の片側を臨時の駐車スペースにしたり、歩く距離が長くなる分カートでクラブハウスまで送迎したりなどの対策を取ることもあるそうです。
ゴルフ場の駐車場では何に注意すべき?
では、ゴルフ場の駐車場を利用するにあたっては、どのような点に注意すべきなのでしょうか。飯島氏は以下のように話します。
「ゴルフ場の駐車場では、昔から車上荒らしが問題視されていました。一度クルマからキャディーバッグを下ろしてクラブハウスの中に入ると、ラウンドを終えて帰り支度を済ませるまで、基本的に駐車場に戻る機会はありません。さらに、大半のゴルファーは『朝スタートして夕方にプレーを終える』という流れで動いているので、どうしても昼間に駐車場に立ち入る人は少なくなります。車上荒らしの犯人は、この監視の目が届きにくいタイミングを見計らって犯行に踏み切るのです」
「コースによっては高級車ばかりが並んでいることもあるため、ゴルフ場の駐車場は車上荒らしにとっては格好の場とされていました。最近は防犯カメラの設置台数が増えたおかげで発生件数は減っています。しかし『貴重品はクルマに置いていかずに持ち歩く』『ハンドルロック・タイヤロックをかける』そして『車内にドライブレコーダーを取り付ける』といった防犯対策はしっかり行っておいた方がいいでしょう」
茨城県の「アジア下館カントリー倶楽部」の担当者にゴルフ場の駐車場における管理の実情について聞いたところ、「当コースの場合は自家用車なら120台近くとめられるようになっており、さらに大型バスも何台か駐車可能です。利用状況としては、平日は全体の半分が埋まる程度。土日祝日ならほぼ満車になる場合も珍しくありません」
「なお、万が一当コースの駐車場内で事故や盗難といったトラブルが発生したとしても、基本的にはお客様同士で解決していただくこととしています。さらに、証拠映像があるとゴルフ場が介入することになって本来のポリシーから外れてしまうので、防犯カメラの設置は行っておりません」 とのことでした。
ちなみに、日本では発進時の事故リスクを減らす意味もあって「後ろ向き」で駐車するのが一般的ですが、ゴルフ場の場合は「前向き駐車」を推奨していることも多いです。
これは「トランクのドアを大きく開けられるスペースを作って、キャディーバッグの積み込みがしやすいようにする」「生垣にクルマの排気ガスがかからないようにする」などの理由から浸透したといわれています。
ゴルフ場でのトラブルと聞くと「打ち込み」や「スロープレー」といったコース内で起きるものが連想されがちですが、駐車場で発生する事象もあります。楽しい1日にするためにも、駐車場内でのトラブルや道中での事故は未然に防いでいきたいものです。
<4/11(金) 11:10配信 ゴルフのニュースより>
ゴルフ場の駐車場において固有? 特有?の考え方があることを始めて知りました。
- 昼間に駐車場に立ち入る人が少ない・・・朝スタートして夕方プレーを終える流れで動くため
- あえて防犯カメラを設置しない・・・お客様同士の事故や盗難トラブルにゴルフ場が介入しないように
- 前向き駐車を推奨している・・・トランクのドアを大きく開けてキャディーバッグを積み込みしやすいように
驚いたのがあえて防犯カメラを設置しないという点です。
これは全てのゴルフ場の駐車場で統一された考え方ではないでしょうが、一部のゴルフ場では防犯面よりもお客様同士のトラブルに介入しないためにあえてそうしているということです。
また、ゴルフはお金持ちのスポーツと言われていますが、駐車場に止める車も高級車が多いということは、それだけ盗難のリスクが高まるということです。
以前は車上荒らしの格好の場とされていたのも納得です。
車上荒らしの多いゴルフ場という致命的な悪評を避ける意味でも防犯カメラ設置やゲート式駐車システムは導入すべきと考えます。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月 8日 10:14)
トクリュウ捜査での指示「トップを狙え」「それって誰?」現場の戸惑い

警察庁は3日、昨年一年間に検挙された「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」の人員が1万105人に上ったと発表した。
トクリュウはSNSなどを通じて犯罪ごとに離合集散を繰り返すアメーバのような犯罪ネットワークを指す。トップダウンでメンバーが明確な暴力団と全く違う形態をとるため、その実態を追うために警察庁が考案した造語だ。
「象徴的だったのは同時期に検挙された暴力団組員などが過去最少の8249人だったこと。組を辞めてトクリュウとして犯罪を続ける者もいるとみられ、暴力団対策からトクリュウ対策に舵を切った警察の見通しの確かさが裏付けられました」(警察庁担当記者)
「匿名SNSを使ってやり取りするのは犯罪者の間ではもはや普通」
警察庁の統計によれば、昨年末時点での全国の暴力団組員は前年末より500人減って9900人。戦後初めて1万人を割り込んだ。一方のトクリュウは様々な分野の犯罪に関わっている。
検挙された1万人超のうち、最多は口座の譲り渡しなどのマネーロンダリングなどを取り締まる犯罪収益移転防止法違反の3293人。ほかは詐欺が2655人、窃盗991人、薬物事犯917人、強盗348人などだった。
「最近の警察発表では『トクリュウとみて捜査している』というのが決まり文句になってきました。匿名SNSを使ってやり取りするのは犯罪者の間ではもはや普通のこと。トクリュウではない組織犯罪の方が肌感覚では少ない」(同前)
「トップを狙え」と言われても...現場には戸惑いの声も
警察がトクリュウ捜査に本腰を入れ始めたのは、死者まで出た、ルフィを名乗る人物が率いる集団による全国での強盗事件がきっかけだった。
SNSで募集した実行役に強盗をさせたり、甘い言葉で拠点であるフィリピンに連れ去った男女を使い特殊詐欺も手がけた。当時の警察庁長官が大号令をかけ、フィリピン当局を動かしてグループ上層の逮捕にこぎ着けた。
「前長官は一貫して刑事畑を歩んできた警察官僚。刑事分野には幅広い関心を持ってきたが、任期の終わり頃には口をあければ『トクリュウ』の話ばかり。矢継ぎ早の指示に幹部も必死だった」(警察関係者)
思いは現職の長官も同様だ。今年1月末の就任会見でもトクリュウ対策を喫緊の課題とし、「違法なビジネスモデルの解体に取り組みたい」と意気込んだ。ただ、空回りの感も。
「長官はじめ幹部連中の口癖は『トクリュウの下っ端ではなくトップを狙え』。ですが、警察や暴力団と違って明確なトップがいないのがトクリュウの特徴。現場には『トップって誰?』という戸惑いもあるようです」(同前)
まずは固い頭をほぐすところからスタートのようだ。
<4/11(金) 11:12配信 文春オンラインより>
どこの企業や組織においてもトップダウンの指示が的外れなことは多々あります。
有能なトップからの適切な指示であれば、部下を無駄なく効率的に動かすことができるかもしれませんが、そうではない場合、部下は無駄な動きが多くなってしまい、結果も出ないことが多いでしょう。
記事の最後に「まずは固い頭をほぐすところからスタート」とありますが、昔は○○だった、普通は△△だなど、凝り固まった頭の人の考え方を変えようとするのは至難の業です。
営業は夫のように外に出て行き、事務は奥さんのように家を守るや女性だから××など、いまだに昭和の感覚から抜け出せていない発言を聞くと悲しくなります。
こういった人は年代的に50代以上に多く、何らかのハラスメント(パワハラ、セクハラ、モラハラ、マタハラなど)を常に周囲に行っている可能性が高いように個人的には思います。
昨年「不適切にもほどがある!(ふてほど)」というテレビドラマが話題になり、2024年の「新語・流行語大賞」を受賞しました。
コンプライアンスが厳しい令和時代(2024年、低成長期)とそうではなかった昭和時代(1986年、安定成長期)を舞台とするタイムスリップものでしたが、ハラスメント傾向の強い人たちはあのドラマを見て今は息苦しい時代だ、昔はよかったと感じた人が多かったような気がします。
そして、昭和時代のどこに問題があり、何が悪かったのかということを理解できない、または理解しようとしていない人たちではないでしょうか。
また、彼らは自分を有能なアイデアマンだと勘違いする傾向にあるように思います。
あれはこうしたらどうか? これはどうだろう? それはこうすべきだ、など次々に浮かんだアイデアを部下に押しつけます。
そのアイデアが優れていれば良いのですが、そうではないケースがほとんどで、その都度部下たちは振り回され、無駄な作業が増えていきます(それが無駄な定例業務に変わっていくことも・・・)。
一般的な社会人で、多少の経験と常識を有していればすぐに判断できそうな事案に対し、的外れな検討を指示します。
そして、自分では決断できず責任もとらない、部下の手柄は横取りする、どこの企業でも思いつく人がいるでしょう。
こういった人たちに信頼する相手がいれば、その人から指摘してもらう、注意してもらう、助言してもらうことができれば、考え方や態度が改善される可能性があります。
しかし、こういった人たちほど役職や地位が高くなり、周囲にはイエスマンしかおらず、裸の王様状態に陥る傾向があります。
人から注意されること、注意してもらえることは、本当は有難いことだと気付ける人はなかなかいません。
人に注意するのはエネルギーが要りますし、相手からは嫌われる可能性もありますから、できればしたくないことです。
嫌いな相手に対してなら尚更で、自分が注意しなかったことで相手がいつか恥をかくことになっても知ったことではありませんし、それを願うことも不自然ではありません。
親やお世話になった上司や先輩など相手の意見に耳を傾けられる相手がどれだけいるか、ということもその人がこれまでに築いてきた財産と言えるでしょう。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月 1日 14:53)